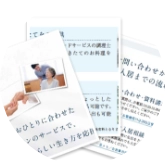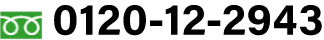高齢者がお風呂に入るのを助ける介護用品の種類と特徴、正しい選び方
入浴は体を清潔に保つだけでなく、心身を癒すための大切な時間です。
しかし、高齢者になると身体能力が衰えてくるため、入浴するのにも介助が必要になってきます。
足元が滑りやすいお風呂場は転倒などのリスクがあり、安全に入浴を行うためには介護用品が役立ちます。
そこで今回は、お風呂用の介護用品を導入するメリット、種類と特徴、選び方のポイントなどについてご紹介します。

入浴用の介護用品を使用するメリット
高齢者の入浴を補助する介護用品は、うまく活用すると被介護者だけでなく介護者にもメリットをもたらします。どのようなメリットがあるのか、見ておきましょう。
被介護者側のメリット
入浴用の介護用品を使用すると、被介護者の肉体的な負担を軽減できるため、入浴時の動作がスムーズになるというメリットがあります。
「体を洗う」、「浴槽をまたぐ」といった動作には、筋力が必要になるため肉体的な負担がかかります。入浴用の介護用品はこうした動作をサポートし、被介護者の入浴を手伝う商品です。
もう一つのメリットとして挙げられるのは、入浴時の事故軽減につながるという点です。浴室内は滑りやすく、転倒により浴槽で溺死してしまう高齢者もいます。
介護用品を活用すると、転倒のリスクを軽減することが可能です。
介護者側のメリット
高齢者の入浴を補助する介護者にとって、足場が悪く滑りやすい浴室での作業は重労働です。
浴槽用の手すりや入浴用の椅子など、介護用品を使うと被介護者が自分でできることが増えるため、介護者の肉体的な負担軽減にもつながります。

ご自宅での生活に不安を感じているあなたへ
無料で有料老人ホームイリーゼの
資料をお送りしています
入浴を補助する介護用品の種類
椅子や手すり、すのこなど、入浴用の介護用品にはさまざまな種類があります。
それぞれの商品の特徴や使い方、向いている人を解説します。
椅子
いわゆる「風呂椅子」という入浴用の椅子で、脚力が低下して立ち上がりなどが困難な人が、一人で入浴する場合におすすめです。
種類がある中でも、洗体・洗髪時に座る「シャワーチェア」という椅子が一般的です。
肘掛けがあるタイプやないタイプ、背もたれがあるものや、折り畳みできるものまで用途に応じてさまざまなタイプのものがあります。
例えば、座位が安定しない人であれば「背もたれや肘掛け付きのもの」、浴室が狭い場合は「折り畳みできるもの」や「座面が回転するもの」といった具合に、被介護者と浴室の状況に合わせた商品を使用すれば、スムーズな入浴介護ができるでしょう。
また、「シャワーキャリー」と呼ばれる車椅子タイプの椅子は、介助されて入浴する人向けの介護用品です。
シャワーキャリーを使えば、脱衣後そのまま浴室に移動してシャワーを浴びられるため、車椅子から移乗する手間がなくなり、介護者の負担を軽減できます。
また、背もたれや肘掛けが付いたものもあるなど、被介護者の身体能力に合わせて選べる点も魅力です。
浴槽内で椅子や踏み台として使用する「浴槽内椅子(浴槽台)」という介護用品もあります。
浴槽の中に置いて腰掛けることができるため、立ち上がりやすくなるのがメリットです。
浴槽から立ち上がる際にバランスを崩しやすい人が、一人で入浴する場合におすすめです。
浴槽用の手すり
被介護者が一人で入浴できるものの、自力で立ったり浴槽をまたいだりする動作に不安がある場合は、「浴槽用の手すり」を取り付けると良いでしょう。
入浴に関する一連の動作を補助できるため、滑りやすい浴室での転倒や、浴槽内で溺れるリスクを下げることができます。
浴槽用の手すりは、浴槽のふちを挟み込む形で直接取り付けます。
グリップ(持ち手)がループの形になっていると、浴槽の中と洗い場のどちらで姿勢が不安定になっても、グリップをつかめるので安心です。
入浴台(バスボード)
浴槽の端と端に渡して置く板のことで、被介護者が自力で立ったり、浴槽をまたいだりする動作に不安がある場合におすすめの介護用品です。
入浴台に腰掛けることによって体を安定させてゆっくりと湯船に入れます。
すのこ・すべり止めマット
浴室内が滑りやすく転倒する危険性がある場合や、脱衣所と浴室に段差がある場合は「すのこ」や「すべり止めマット」を設置するのがおすすめです。
すのこには高さの調節機能が付いたものがあり、脱衣所と浴室の段差をなくすことができます。シャワーキャリーでの移動もスムーズに行えるでしょう。
ただし、木製のすのこは完全に乾燥させるのが難しく、滑ってしまうおそれがあります。不安な人は、プラスチック製のすのこかすべり止めマットを使用してください。
なお、すべり止めマットには浴槽内に敷くタイプもあります。
入浴用介助ベルト
入浴時に被介護者は裸なので、介助を行う介護者が十分な力をかけられず、体を持ち上げるのが難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、「入浴用介助ベルト」を披介護者に装着することをおすすめします。
持ち手のあるベルトを被介護者の腰部に着けると、介護者が力を入れやすくなり、浴槽での被介護者の立ち上がりや移動をスムーズに行えます。
入浴用リフト
被介護者が手すりや入浴台などを使っても浴槽に出入りするのが難しくなったら、入浴用リフトの設置も視野に入れましょう。
入浴用リフトは、高齢者を乗せて浴槽への出入りをサポートする機械です。
簡単に設置できるものから、大がかりな工事が必要なものまでさまざまなタイプがあり、費用も異なります。
浴槽への出入りを安全に行えるため、被介護者だけでなく、介護者の肉体的な負担を軽減できるというメリットがあります。
ただし、浴室や浴槽が小さいと設置自体が難しい場合もあるため、注意が必要です。
簡易浴槽
被介護者が寝たきりの状態などで、浴室までの移動が困難な場合は、「簡易浴槽」の使用をおすすめします。自室で入浴できる「ポータブル浴槽」とも呼ばれる介護用品です。
立て掛け式から、空気式、折り畳み式までさまざまなタイプがあります。
浴槽のほかに、エアーポンプや排水用のホースなどが付属しており、洗髪機能付きの高機能なものもあります。
簡易浴槽を使用する際は、ホースの距離に気を配る必要があります。ホースが長すぎると、お湯の温度が下がってしまうからです。
また、部屋の中で入浴するため、水蒸気や換気にも気を配りましょう。
当然ながら、入湯の際には補助が必要です。
入浴用の介護用品を選ぶポイント
入浴用の介護用品を選ぶ際には、被介護者の身体状況以外にも浴室の環境など、考慮すべきポイントがあります。
被介護者の身体状況に合わせる
入浴用の介護用品を購入する際は、被介護者の症状に合わせて検討していく必要があります。
まず、被介護者の要介護度をきちんと把握しておきましょう。
要支援1~2や要介護1程度で、補助があれば一人でも入浴できる場合は、手すりやシャワーチェア、浴槽内椅子などを使ったサポートが必要です。
要介護1以上で、一人での入浴が困難な場合は、介護者が入浴のサポートをすることも想定し、入浴台やシャワーキャリー、入浴用リフトなども視野に入れましょう。
次に、被介護者の体への負担や、転倒防止のリスクを下げるために、被介護者の体の大きさに合わせた介護用品を選びましょう。
浴室の広さも考慮し、介護者と被介護者の間に十分なスペースを取れるようにするのも重要です。介護者側が被介護者を無理なく介護できるポジションや、動けるスペースを確保しておくと、負担を少なくすることができます。
浴室の環境を考慮する
実際に介護用品を選ぶ際は、事前に浴室や浴槽の寸法を測っておきましょう。
測ると良いのは、出入り口の広さ、洗い場の広さ、浴槽の高さ・幅、段差などです。
入浴台や入浴用リフトなどは、サイズによってうまく配置できない場合もあります。
すのこなど、オーダーメイドが可能なものもありますので、浴室の寸法を測っておくと丁度よいサイズのものを準備できます。
すのこやすべり止めマットを使用する場合は、床の材質も考慮すると良いでしょう。
湯けむりの中でも見えやすい色を選ぶ
高齢者は視力の悪い人が多く、浴室内は湯気で物が見づらくなることもあります。手すりなどを設置する際は、湯けむりの中でもできるだけ目立つ色のものを選ぶのがポイントです。

ご自宅での生活に不安を感じているあなたへ
無料で有料老人ホームイリーゼの
資料をお送りしています
介護サービスもうまく活用して介護の負担を減らそう
入浴用の介護用品の中には、指定された事業者から「特定福祉用具」として自己負担額1割で購入できるものがあります。
「特定福祉用具販売」という介護サービスで、支給対象者は、要介護認定を受けた要支援1~要介護5までの人です。年間10万円(税込)を上限まで利用することができますが、それ以上は自己負担になります。
介護にはお金もかかりますので、サービスを利用したい人はケアマネジャーに相談してみましょう。
入浴は、日々の生活の中で欠かせないものです。被介護者がより快適な生活を送るために、介護者の負担を減らすことも考えて、適した介護用品を選びましょう。
※本記事の内容は、公的機関の掲出物ではありません。記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の情報を保証するものではございません。