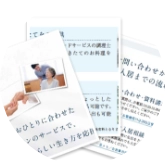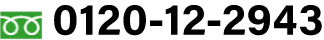高齢者虐待を防止するには?介護現場の実態と今後の解決策
高齢化が進み、被介護者の人数が増えるとともに、高齢者虐待の問題が深刻化しています。しかも自宅や施設、病院など、場所を問わず、さまざまな現場で起きているのが特徴です。
では、実際に高齢者虐待の件数はどれくらいあるのでしょうか。そもそも、なぜ虐待が起こるのでしょうか。
今回は、高齢者の介護に携わっている人たちに向けて、高齢者虐待の実態と解決策をご紹介します。
大切な家族を虐待から守るため、ぜひ最後までお読みください。

増えている高齢者虐待
厚生労働省の調査結果によると、高齢者虐待の件数は年々、増加傾向にあります。
令和3年度と令和4年度の当該件数を中心に、高齢者虐待の実態を見てみましょう。
介護施設による虐待の実態
介護施設で虐待の事実が認められた事例件数は、令和4年度だけで856件です。令和3年度の739件と比較すると、件数で117件、増減率では15.8パーセント増加しています。
・被虐待者の年齢の傾向
令和4年度における被虐待者の総数は1,406人(1件の事例に対し被虐待高齢者が複数のケースを含む。以下「複数回答」と記述)ですが、そのうち85~89歳が23.8パーセント(335人)、90~94歳が23.5パーセント(330人)と、2つの世代で半数近くを占める傾向にあります。
・虐待の事実が認められた介護施設の種類
介護施設における令和4年度の虐待事例は、特別養護老人ホームが274件(856件中)と、全体の32パーセントを占め最多です。以下、有料老人ホームが25.8パーセント(221件)、グループホームが11.9パーセント(102件)、介護老人保健施設が10.5パーセント(90件)という順で続いています。
家族や親族による虐待の実態
・令和3年度から令和4年度の増減率
令和4年度に「家族や親族から虐待を受けた、又は受けたと思われた」と市区町村が判断した高齢者虐待の事例は、全部で16,669件です。これは、令和3年度の16,426件と比べて243件増えており、増減率では1.5パーセントと微増傾向にあります。
・虐待者と被虐待者の関係
令和4年度の虐待事例16,669件のうち、息子が全体の39パーセント(6,982件)を占め最多です。以下、夫の22.7パーセント(4,070件)、娘の19.3パーセント(3,465件)の順に続いています。
一方、同居・別居の状況を見てみると、虐待者とのみ同居している人が52.8パーセント(9,020人)、虐待者および他家族と同居している人が34パーセント(5,814人)であり、実に86.8パーセントもの被虐待高齢者が虐待者と同居しているという結果が出ています。
無料で有料老人ホームイリーゼの
資料をお送りしています
虐待の種類
続いて、身体的虐待をはじめとする「五つの虐待」の特徴と具体例、令和4年度の各当該件数(複数回答)について見てみましょう。
身体的虐待
介護高齢者に対して、暴力的行為を働いたり、威嚇したりするのが身体的虐待です。また、緊急時などのやむを得ない場合以外の身体拘束、本人に不利益となる強制的な行為や行動・言動の制限なども身体的虐待と判断されます。
主な具体例には、「殴る・蹴る等の暴行」「本人が嫌がっている状態で意図的にベッドや車椅子に拘束する」「過剰な投薬による身体拘束」などがあります。
身体的虐待は、五つの虐待の中で最も高い割合を占め、介護施設で57.6パーセント(810人)、家族や親族による介護(以下「在宅介護」と記述)で65.3パーセント(11,167人)という数字が、令和4年度の当該件数として報告されています。
介護等放棄
日常生活を送る上で必要な介護や支援を怠り、高齢者の生活環境を悪化させるほか、心身状態にも支障をきたすような行為を働くのが介護等放棄です。
主な具体例として、「入浴や排泄の世話をせず、不衛生な環境で生活させる」「介護・医療のために必要な用具を使用せず、身体機能の低下を招く」などが挙げられます。
介護施設で23.2パーセント(326人)、在宅介護で19.7パーセント(3,370人)という数字が、令和4年度の介護等放棄件数として報告されています。
心理的虐待
心理的虐待は、暴言・威圧・侮辱・脅迫・無視など、言葉の暴力もしくは威嚇的な態度により、高齢者の意欲や自立心を低下させる行為です。
「罵声を浴びせる」「嘲笑する」「尊厳を著しく傷つける誹謗中傷」などが主な具体例として挙げられます。
介護施設で33パーセント(464人)、在宅介護で39パーセント(6,660人)という数字が、令和4年度の心理的虐待件数として報告されています。
性的虐待
わいせつ行為をはじめ、性行為の強要や性的暴力、性的羞恥心を喚起する行為の強要、性的嫌がらせなどが性的虐待に当たります。
「キス・愛撫・セックスの強要」「着衣をさせず丸裸にさせる」などが具体例です。
介護施設で3.5パーセント(49人)、在宅介護で0.4パーセント(65人)という数字が、令和4年度の性的虐待件数として報告されています。
経済的虐待
本人の合意がないまま財産や金銭を取り上げたり、それらの権利を不正に使用したりするのが経済的虐待です。また、日常的に必要とされる金銭を渡さない・使わせないといった行為も、経済的虐待に当たります。
主な具体例には、「年金・預貯金を取り上げる」「預貯金やカード等を着服・窃盗する」「不動産・有価証券等を無断で売却する」などがあります。
介護施設で3.9パーセント(55人)、在宅介護で14.9パーセント(2,540人)という数字が、令和4年度の経済的虐待件数として報告されています。

虐待が起こる理由
介護施設と在宅介護で虐待が起こる要因の中から上位五つをピックアップしてご紹介します。
介護施設の場合
介護施設で虐待が起こる理由は、「教育・知識・介護技術等に関する問題」が全体の56.1パーセントを占め最多です(480件)。以下、「職員のストレスや感情コントロールの問題」が23パーセント(197件)、「虐待を行った職員の性格や資質の問題」が22.5パーセント(193件)、「倫理感や理念の欠如」が 17.9パーセント(153件)、「人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ」が11.6パーセント(99件)という順で続いています。
在宅介護の場合
在宅介護で虐待が起こる理由は、被虐待者の「認知症の症状」が全体の56.6パーセントを占め最多です(9,430件)。以下、虐待者の「介護疲れ・介護ストレス」の54.2パーセント(9,038件)、「理解力の不足や低下」の47.9パーセント(7,983件)、「知識や情報の不足」の47.7パーセント(7,949件)、「精神状態が安定していない」の47パーセント(7,840件)の順に続いています。
無料で有料老人ホームイリーゼの
資料をお送りしています
高齢者の虐待を防止する取り組み
ここまでのデータを踏まえた上で、高齢者虐待防止法に触れながら、厚生労働省が公表した具体的な取り組みと、被介護者と家族にできる対策をお伝えします。
高齢者虐待防止法
虐待の定義を明確にし、通報・相談の窓口を設けることで、高齢者虐待の早期発見および防止・保護につなげるために制定されたのが「高齢者虐待防止法」です。「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が正式名です。
高齢者虐待防止法は、2005(平成17)年にできた法律で、翌年の2006(平成18)年4月から施行されています。同法の中では、被虐待者の対象を65歳以上とした上で、前述した五つの虐待をそれぞれ定義し、明確化しています。また、高齢者虐待の防止が目的のため、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、窓口となる当該の市町村に通報することが義務づけられています。
具体的な取り組み
高齢者虐待は年々増加傾向にあるため、虐待防止に向けた取り組みも強化されています。特に、2017(平成29)年には、「介護事業者向け」「市町村職員向け」「地域住民向け」という3つの柱が見直されました。
・介護事業者向け
介護施設は、内部の介護スタッフだけの閉ざされた場所でもあり、虐待の事実が明るみに出にくい可能性が考えられます。そのため、地域住民などとの積極的な交流を図ったり、地域支援事業の介護相談員派遣事業を積極的に活用したりすることで、「外部に開かれた施設」を目指すために見直されています。
一方、介護施設内で影響力のある職員(施設長レベル)を対象に、研修や教育を実施し、法制度・介護技術・認知症への理解、職員のストレス対策、虐待事案が発生した場合の迅速な報告体制の整備なども推進しています。
・市町村職員向け
都道府県側が市町村の職員を対象とした法制度などの研修を実施するほか、都道府県や市町村のWebサイトを活用して、通報窓口の存在を広める活動も取り入れています。Webサイト以外にも、市町村や地域包括支援センターが発行する広報誌・リーフレット・健康カレンダー・暮らしのガイドブックなどへの掲載が検討されています。
・地域住民向け
市町村の職員同様、地域住民向けのリーフレットを作成することで、高齢者の虐待防止や通報窓口の周知徹底が強化されています。そのほか、従来から実施していた「地域住民向けのシンポジウム」の開催も引き続き行い、第三者が高齢者虐待への理解を深め、介入できる機会を増やしています。
被介護者と家族にできること
2004(平成16)年に医療経済研究機構がまとめた「家庭内における高齢者虐待に関する調査」によると、虐待されても自覚のない高齢者は29.8パーセント、自分が虐待しているという自覚のない虐待者は54.1パーセントという結果が出ています。つまり、当事者全員が虐待を認識しているとは限らないため、注意深く対応する必要があるということです。
例えば、「体のあざが日に日に増えている」「精神的なストレスで食事量が減った」など、被介護者のサインを見逃さないことが重要です。
また、地域包括支援センターなどに相談すれば、適切なアドバイスを受けられる場合もあるので、日ごろから相談窓口の連絡先を見える位置に置いておきましょう。

高齢者虐待への理解を深める努力が防止につながる
高齢者虐待は、認知症の有無や介護度などによっては本人が自覚できなかったり、逆に被害妄想だったりする場合があるため、一概に虐待と判断しにくいケースも考えられます。また、介護施設や在宅介護においても、故意に暴力を振るったのではなく、高齢者を危険から守ろうとした結果、傷つけてしまったというケースもあるでしょう。
しかし、実際に虐待が起きているのが現状です。「自分は関係ない」「うちは大丈夫」と思わず、高齢者虐待に対する理解を深める努力を怠らないことが大切です。
無料で有料老人ホームイリーゼの
資料をお送りしています
この記事の監修者

在宅緩和ケア充実診療所・機能強化型在宅療養支援診療所
城北さくらクリニック
院長 犬丸秀雄
HP:http://houmon-shinryo.jp/jsc/
日本大学医学部卒業後、日本大学板橋病院(麻酔科・救命救急・ICU)を経て、赤塚駅前クリニックを開業し往診も行う。平成24年より、東京都練馬区を中心に訪問診療専門の診療所を開設。
24時間体制、コールセンター設置等を整備し、医師11名・看護師5名(令和3年6月現在)でご自宅や施設へ訪問診療を行っている。
※本記事の内容は、公的機関の掲出物ではありません。記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の情報を保証するものではございません。